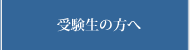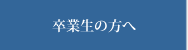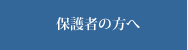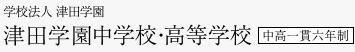学力向上システム
- TOP >
- 学校紹介 >
- 学力向上システム
学力向上システム
本校では、一人一人の個性や目標に応じたきめ細かい進路指導を行っています。中学課程では基礎基本を徹底し、夏期・冬期の長期休暇中には、より発展的な進学課外を開講しています。高校課程では、大学入試対策として進学課外や特別講座、それぞれの生徒に合った個別指導を行っています。志望校に現役合格するために必要なことは、目標から逆算して1つ1つ着実に取り組むことです。本校ではその実現に向けたサポートを行っています。
「進学課外について」
中学1~3年次は、実力養成を目的に応用問題を中心に取り組みます。4~6年次は、国公立大学や難関私立大学への受験に特化した発展的な講座を開講しています。

「特別講座について」
現役の大手予備校講師を招いて特別講座を開講しています。大学入学共通テストや国公立大学・難関私立大学の二次試験を見据え、最新の傾向や入試問題を解く道筋や解法のテクニックを養成します。
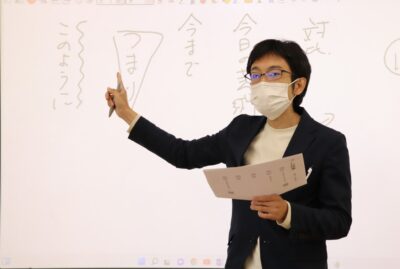
「個別指導について」
本校では定期的に二者懇談を行っています。また、教育ICTや能率手帳等の活用により、日々の学習状況や勉強に対する理解度や悩みを把握する取り組みを実施しています。生徒の個性や希望、特長を生かした大学・学部や受験方法を提案します。

「勉強合宿について」
卒業生をチューターとして招いて、勉強合宿を実施しています。学習内容だけでなく、受験時の経験談や気持ちの持ち方など学習面意外のこともより身近に感じる卒業生から聞くことができる企画となっています。
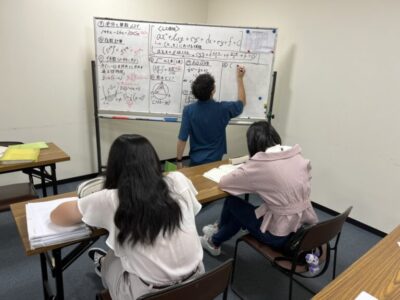
各教科指導方針
- グローバル化に対応できる人材を育成。
- 4技能のバランスが取れた英語力を鍛える。
- 使いながら教える・使うために教える。
- 授業は英語で行うことを基本とする。
- ICTを効果的に利用。
- 「NHK英語講座」「英字新聞」「学校行事」「特別活動」を通じた「教室外」英語環境の充実。
- 到達目標スコア CEFR:B1 TOEICR:550・240(S&W) 160(Bridge) GTEC:463(forSTUDENTS) 英検:2級
- 与えられた文章や図表等の中から、情報を収集したり取り出したりする力を身につける。
- 文章や図表等を整理し解釈する力や、要約して一般化する力を身につける。
- 得た情報をもとに、物事を推し量ったり予測したりする力を身につける。
- 問題解決のための方法や計画(自分の考え)をまとめる力を養う。
- 伝える相手や状況に応じて適切な語彙、表現、構成、文法等を用いることができる力を養う。
- 協働学習により、問題を解決する思考力・表現力を養う。
- ICT(電子黒板)・Chromebook(ノートパソコン)を活用し、自分の考えを発表させることで表現力を養う。
- 調べ学習を行い、発表の場を作る。
- 課題研究(確率に関するものや三角比を利用した校舎の高さ調べ、データの分析など)により、数学を活用する思考力、判断力を養う。
- 数学を活用する問題の演習を行う。
- 実験の方法・目的を理解し、実験器具の正しい使い方を習得し、考察力を身につける。
- ICTを活用し、自然事象・現象に対して科学的な見方・考え方を養い、グループワークにより討議する力や的確に表現する力を身につける。
- 自然事象・現象に興味をもち、探究心を養い、基本的な概念や原理・法則を理解する。
- 自ら進んで調べ、主体的に学習ができる力を身につける。
- わが国の歴史・文化・伝統に興味を持ち、誇りを持つ。他国の文化や伝統を理解し、真の国際人となる。
- 社会的事象に関心を持ち、それらに対して自分の考えを持つ。発表する機会を通して、分かりやすく説明する力を身につける。
- グループワーク・協働学習を通して、周りの人と協力して取り組む力を身につける。
- 音楽の持つ曲想や美しさを感じ取り、それらを生かした表現ができるように指導します。
- 音楽を通し、豊かな発想、構想する能力、基本的技能を身につけるように指導します。
- 音楽の持つ叙情的な力に触れることで、豊かな生活を創造していく意欲や態度を育てます。
- 感性とは、「生まれつき備わった能力ではなく育て高めるもの」との観点に立ち、見る力や感じる力、発想する力や吸収する力を育てます。
- 総合的な見方や考え方を培い、多様な表現方法や造形要素に関心をもち、創意工夫して創造的に表現する能力を育てます。
- 生徒が自ら創り出した作品を鑑賞することを通じて、その成果と課題から生徒自身が学びの視点に気づき共有し合う姿勢を育てます。
- 積極的に運動に親しむ資質や能力を育て、健康の保持増進・体力の向上を図ります。
- さまざまな体育実技や体力測定を通じ、自らの体力を知ることで課題を見つけ、生徒一人ひとりにとって有意義な体育の授業になるように指導します。
- 授業を通じて「協調性」「公正」「責任」「安全管理」を自ら実践できる力を養います。
- 自分の生活の成り立ちを知り、衣食住に関する知識や技術を身につけるように指導します。
- さまざまな実技を通して、創作する喜びやものを大切にする心を育てます。
- 食の選択・管理などを学ぶことで、「食」と社会のかかわりを考え、「食」に対する高い意識を育てます。
- 歴史や伝統を継承してきた日本人の心に触れることで、日本の素晴らしい伝統文化を再確認し、私たちもその継承者の一員であることを自覚させます。
- また、偉人の生き方や考え方に触れることで、日本人としての誇りを持ち、社会のために尽くす心、思いやりの精神を育みます。
- 国際語を身につける中で、その国の文化や考え方に触れ、相対的に日本の文化や物事を考える力を養います。
- 通常授業の枠を超えた「伝統文化に触れる行事」、「マナー講座」、「自然体験活動」などを通し、人間形成に必要な教養、そしてねばり強い心を身につけるように指導します。
- 国際化・情報化が進む社会において、コンピュータを活用する能力を取得し、さらには異国の人々とも交流できる能力を育てます。