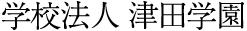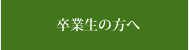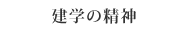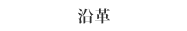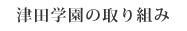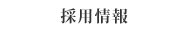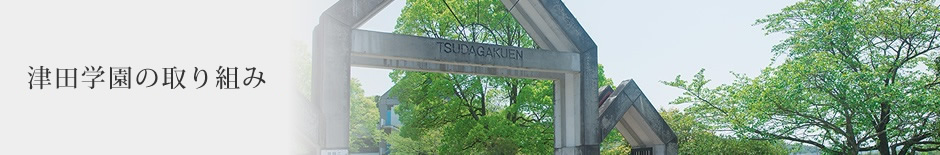- TOP >
- 津田学園の取り組み
津田学園の取り組み
未来を切り拓く、躍動する津田学園の教育活動
児童生徒が将来、グローバル社会で逞しく生き抜く力を養うため、本学園では「教育ICTの大幅な導入と活用」「多様な価値観を尊重し理解するグローバル・マインドの育成」「アクティブラーニングを取り入れた授業の推進」を積極的に取り組み、豊かな人間性を備え、生きる力を身につけた有為な人材の養成を目指しています。 「教育ICT」および「アクティブラーニング」の導入・活用によって、協働的な学習が活発に展開され、学力の向上はもとより、児童生徒の自主性伸長におおいに資するものとなります。 また、「グローバル・マインド育成」の分野では、より実践的な英語力養成を目指し、実践力を身につけ、将来国際社会において活躍できる「力」を備えることができます。 そして、本学園創立以来、教育の基本に捉え、推進している「道徳教育」をより充実させることにより、豊かな人間性を備えた、次世代の社会を牽引することのできるリーダーを育成しています。
教育ICT
 本学園では、平成25年から電子黒板を導入しています。ICTの力を教育に活用する取り組みは大きく加速しており、現在では、小学校・中学校・高等学校ともに全教室に電子黒板を導入、その活用度は国内トップクラスであると自負しています。今後もさらに導入を進めていく予定です。また、タブレット端末(iPad)も積極的に導入し、電子黒板との連動による双方向型の授業を実現しています。これらを活用して「協働的な学習」や「アクティブラーニング」など新しいスタイルの授業も展開しています。
本学園では、平成25年から電子黒板を導入しています。ICTの力を教育に活用する取り組みは大きく加速しており、現在では、小学校・中学校・高等学校ともに全教室に電子黒板を導入、その活用度は国内トップクラスであると自負しています。今後もさらに導入を進めていく予定です。また、タブレット端末(iPad)も積極的に導入し、電子黒板との連動による双方向型の授業を実現しています。これらを活用して「協働的な学習」や「アクティブラーニング」など新しいスタイルの授業も展開しています。
今、教育界は大きな変革期にあるといえます。従来の学力観だけでは未来を生き抜く力を身につけることができないとされ、これからは「得た知識を活用して課題を解決する力」や、「自ら主体的に学ぶ力」を児童・生徒に習得させることが求められています。「協働的な学習」を効果的に行うことで、それらの力を身につけることが可能です。本学園では、従来の講義型の授業ではなく、話し合い、教え合い、学び合い、自らが主体的に参加していくスタイルの授業を積極的に取り入れており、これらの授業で電子黒板やタブレット端末といったICT機器は非常に効果的です。電子黒板とタブレット端末を連動させることで、誰がどのような考え方や意見を持っているのかを簡単に察知することができ、授業を効果的に進めることができます。そしてそれらを分類したり比較したり、さらに考えを深めたりすることで、児童・生徒はどんどん主体的に学ぶことができます。 時代のニーズを捉えながら、本学園は今後もICT機器を活用した新しいスタイルの授業に挑戦していきます。試行錯誤と研究を重ねながら、未来を生きる児童・生徒にふさわしい教育環境を整えていくことを目指します。
グローバル・マインド育成
 魅力に溢れた英語教育を構築し展開するために、本学園では様々な取り組みを行っています。小学校では、外国人講師による英語教育はもとより、子どものための英語4技能検定テストを導入するなど、楽しく学びながら英語の基礎力を身に付けるカリキュラムを展開しています。中学校・高等学校(六年制)においては、大学入試改革の目玉である「英語」の変化に対応するために、特にスピーキングやリスニング、ライティング(自由英作文)の力を身につける必要があるため、多岐にわたる取り組みを実践しています。例えば、外国人講師による英会話授業、NHKラジオ英会話講座の活用、スキットコンテストを中学課程で、エッセイコンテスト(500語以上)を高校課程で毎年参加しています。また、英字新聞による指導やTOEIC-Bridge、TOEICを実施し、より高いレベルの英語力の修得を目指しています。遠足で京都を訪問した際には、外国人観光客へ英語によるインタビューを行うグループワークなども実施しています。高等学校(三年制)では六年制と同様に特別選抜、特別進学、総合進学の全コースでGTEC-for-studentsを受験しています。その結果、外部のスピーチコンテストに積極的に参加する生徒や、難関大学合格に向けて英語雑誌「TIME」を利用した指導を受けている生徒なども見られるようになりました。今後は、幼稚園(現在はすでに外国人講師による英会話を実施)においても楽しく実践的な英語教育を展開していきます。
魅力に溢れた英語教育を構築し展開するために、本学園では様々な取り組みを行っています。小学校では、外国人講師による英語教育はもとより、子どものための英語4技能検定テストを導入するなど、楽しく学びながら英語の基礎力を身に付けるカリキュラムを展開しています。中学校・高等学校(六年制)においては、大学入試改革の目玉である「英語」の変化に対応するために、特にスピーキングやリスニング、ライティング(自由英作文)の力を身につける必要があるため、多岐にわたる取り組みを実践しています。例えば、外国人講師による英会話授業、NHKラジオ英会話講座の活用、スキットコンテストを中学課程で、エッセイコンテスト(500語以上)を高校課程で毎年参加しています。また、英字新聞による指導やTOEIC-Bridge、TOEICを実施し、より高いレベルの英語力の修得を目指しています。遠足で京都を訪問した際には、外国人観光客へ英語によるインタビューを行うグループワークなども実施しています。高等学校(三年制)では六年制と同様に特別選抜、特別進学、総合進学の全コースでGTEC-for-studentsを受験しています。その結果、外部のスピーチコンテストに積極的に参加する生徒や、難関大学合格に向けて英語雑誌「TIME」を利用した指導を受けている生徒なども見られるようになりました。今後は、幼稚園(現在はすでに外国人講師による英会話を実施)においても楽しく実践的な英語教育を展開していきます。
アクティブラーニング
 今、注目されているアクティブラーニングを活用した授業を積極的に導入して、児童生徒自らが課題を見いだし、その解決に向けて主体的・協働的に取り組む学習活動を展開しています。各教科においては、タブレット端末(iPad)や電子黒板などのICT機器を積極的に活用して、調べ学習・発表会、また英語スピーチをはじめ、英語弁論発表、各種プレゼンテーションといった、グループワークやディスカッション型学習活動の機会を多く設定しています。こうした活動などから、机上学習だけでは養うことのできない思考力・判断力など総合力を磨くよう努めています。ICT機器を活用した授業は、これらアクティブな学びとの親和性が高く、うまく活用できれば児童生徒の学びに対する主体性をますます深めることが可能になります。
今、注目されているアクティブラーニングを活用した授業を積極的に導入して、児童生徒自らが課題を見いだし、その解決に向けて主体的・協働的に取り組む学習活動を展開しています。各教科においては、タブレット端末(iPad)や電子黒板などのICT機器を積極的に活用して、調べ学習・発表会、また英語スピーチをはじめ、英語弁論発表、各種プレゼンテーションといった、グループワークやディスカッション型学習活動の機会を多く設定しています。こうした活動などから、机上学習だけでは養うことのできない思考力・判断力など総合力を磨くよう努めています。ICT機器を活用した授業は、これらアクティブな学びとの親和性が高く、うまく活用できれば児童生徒の学びに対する主体性をますます深めることが可能になります。
また、タブレット端末(iPad)を活用し、電子黒板と連動させた対話的で協働的なスタイルの学びは、時間的空間的制約を越えるというICT機器ならではの特性が有効に作用します。ただ教師の話を聞き、黒板をノートに写し取るという授業スタイルだけではなく、児童生徒が主体的・能動的に取り組むことができる深い学びをつくりだしていくことができます。今後、さらに進んでいくグローバル化に対応すべく、固定概念の殻を破り、積極的かつ柔軟に世界で活躍できる能力を養っていきます。
道徳教育
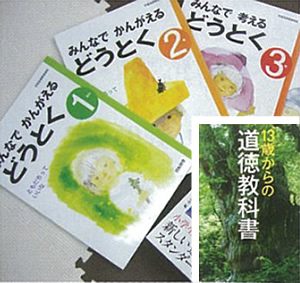 本学園は「道徳教育の推進」を教育の重要な柱の一つに据え、児童・生徒が自己や家族を慈しみ、また郷土や国家を愛して、将来広く世界の平和と人類の幸福のために貢献する人間となるという信念を持って自身の進むべき道を切り開いていく力を培うことを目的としています。
本学園は「道徳教育の推進」を教育の重要な柱の一つに据え、児童・生徒が自己や家族を慈しみ、また郷土や国家を愛して、将来広く世界の平和と人類の幸福のために貢献する人間となるという信念を持って自身の進むべき道を切り開いていく力を培うことを目的としています。
そしてその目的を実現するために、さまざまな取り組みをしています。
第一に、学園に学ぶ者すべてが自然や神への畏敬の心を抱き、他者に対して謙虚な気持ちで接する「真の優しさ」を培うため、「自然や他者に対する思いやりの心」・「礼儀作法」・「規律を守ること」の大切さを教え、生活全般の中で、行動を通じて体現することができるようあらゆる場面を通じて実践させています。
第二に、児童・生徒の発達段階に応じ、それぞれのカリキュラムに添った「道徳の時間」を設定し、小・中学校生徒に対しては、道徳教科書を、高校生に対しては資料を活用して授業を展開しています。
現在は、「偉人に学ぶ」ことをテーマに、その人がさまざまな状況の中で、どのような信念に基づき、どのように行動して困難に立ち向かい、切り拓いて自身の人生を賭けつつ社会に貢献し得たのかを学び、児童生徒自身が将来正しく充実した人生を歩み、社会から必要とされる「真の力」を備えた人間となれる資質を養うことに努めています。
また、平成26年には「津田学園ふるさとの森」を設立、3000本の木々を植樹してそれらが地中深くに根を張っている姿から、あらゆる生命を包み込んだ「自然」の偉大さと、「逞しい生き方」を学園に関わるすべての人々が感得し、心安らぐ「ふるさと」として回帰できる場を設けました。